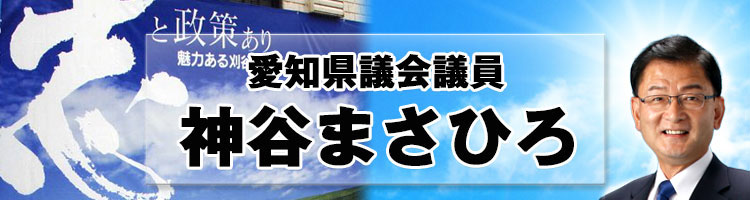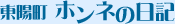私の所属する建設委員会が開催され、1月28日に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受けて4つの角度から質問をしました。
【質問1】
本県はものづくり産業を支える日本一の県であり、道路交通の安全確保が不可欠です。道路陥没は県民の生命・財産を脅かすだけでなく、社会経済活動にも大きな影響を及ぼします。本県が管理する流域下水道において、今回の事故を受けてどのような対応を行ったのか、また、県内市町の対応状況についてお聞かせください。
【答弁1】
国は大規模下水道管の緊急点検を7都府県に要請しました。本県は対象外でしたが、矢作川流域下水道が基準に達したため自主点検を実施。管径2,000mm以上の約39kmについて、路面やマンホール内から点検を行い、異常は確認されませんでした。県内自治体では名古屋市を含む30市町が点検を実施し、異常箇所の有無を確認しました。
【質問2】
大きな事故を防ぐためには、毎年、計画的に点検調査を行うことが重要だと思います。そこで、本県が管理する流域下水道管の通常の点検調査はどのように行われているかをお尋ねします。
【答弁2】
県が管理する流域下水道管きょは、国のガイドライン等に基づいて、10年に1回以上の頻度で人やカメラを使い、下水道管路内の劣化状況を把握する調査を行っています。また、腐食の恐れが大きい箇所は、5年に1回以上の頻度でマンホールの中から異常の有無を確認する点検を実施しています。
【質問3】
下水道管の破損以外にも、地盤の緩みなどによる道路陥没の危険があります。安全な道路環境を維持するには、異常兆候の早期発見が不可欠です。道路管理者による日常点検を確実に実施するとともに、道路利用者からの情報を幅広く収集し、迅速に対応することが求められます。本県における常日頃の道路管理者の取組や、道路利用者からの情報収集の仕組みについてお聞かせください。
【答弁3】
本県では、全路線で週1回以上のパトロールを実施し、異常箇所の応急措置を行っています。また、2017年度から緊急輸送道路などで地中レーダー探査を行い、空洞を発見した場合は埋め戻しなどの対応を実施。さらに、道路緊急ダイヤルやLINEアプリを活用し、24時間体制で道路利用者からの情報を受け付け、迅速な対応に努めています。
【質問4】
八潮市の事故を受け、老朽化した上下水道施設の更新に対応するため、上下水道の一本化を早急に進めるべきとの意見が出ています。西三河地域で進められている上下水道一本化は、県と市町が事業を統合することで経営基盤を強化し、施設の老朽化対策を推進する有効な手段です。そこで、西三河地域における上下水道一本化の取り組み状況と、今後の予定についてお聞かせください。
【答弁4】
西三河地域の上下水道一本化については、準備会で施設の共同化や管理の一体化、一本化の組織形態を検討しています。現在、行政界を越えた施設の統廃合について協議を進めています。今後は、来年度中の協議会設立を目指し、基本方針案を策定しながら、具体的な統合に向けた準備を進めてまいります。